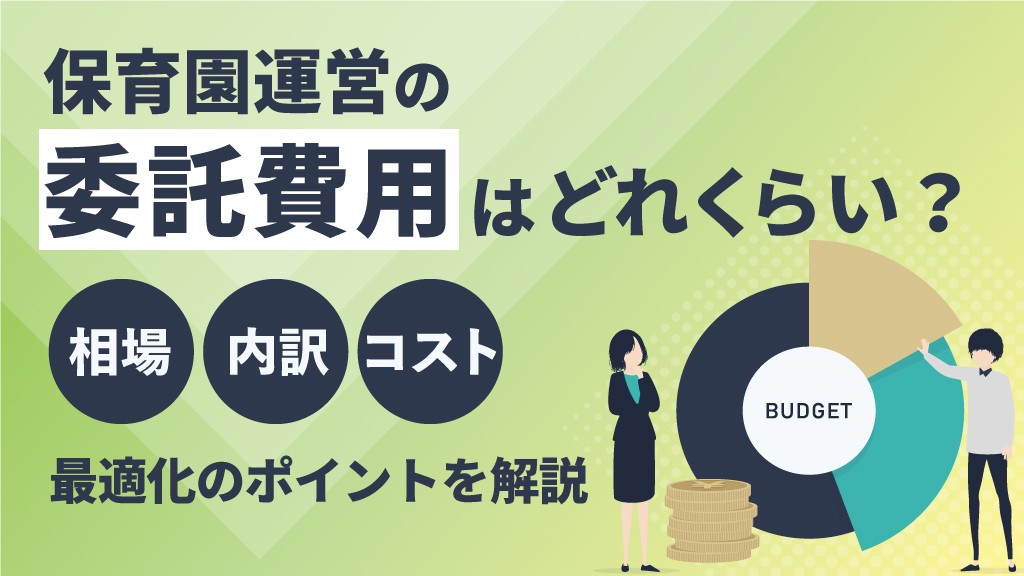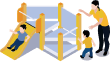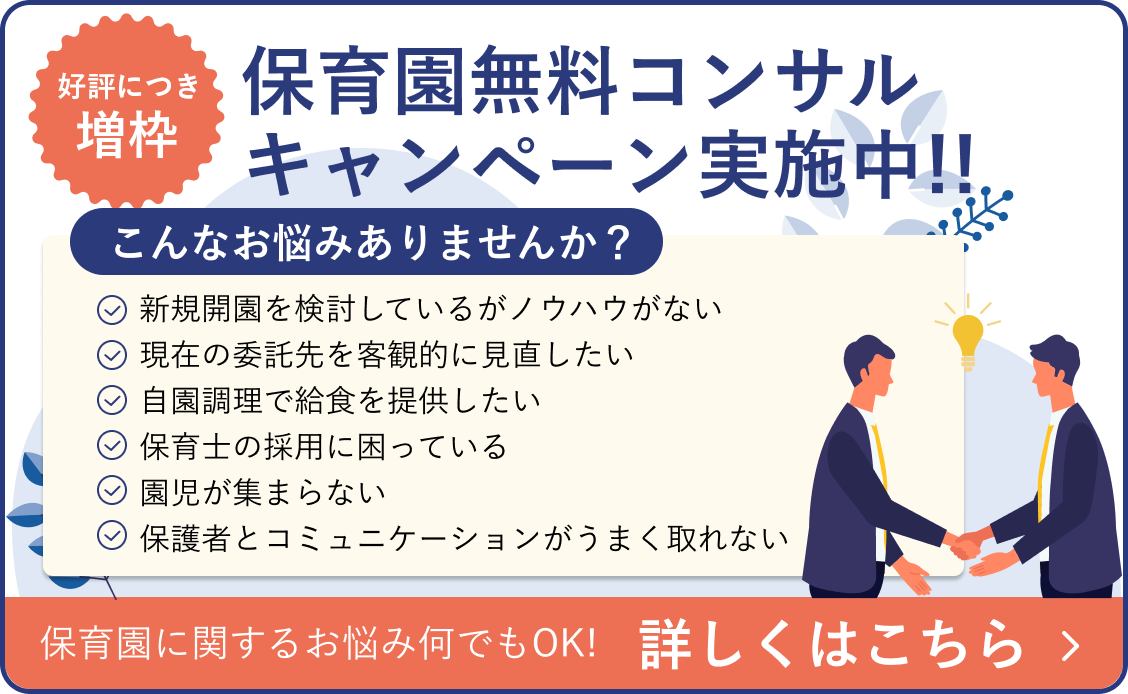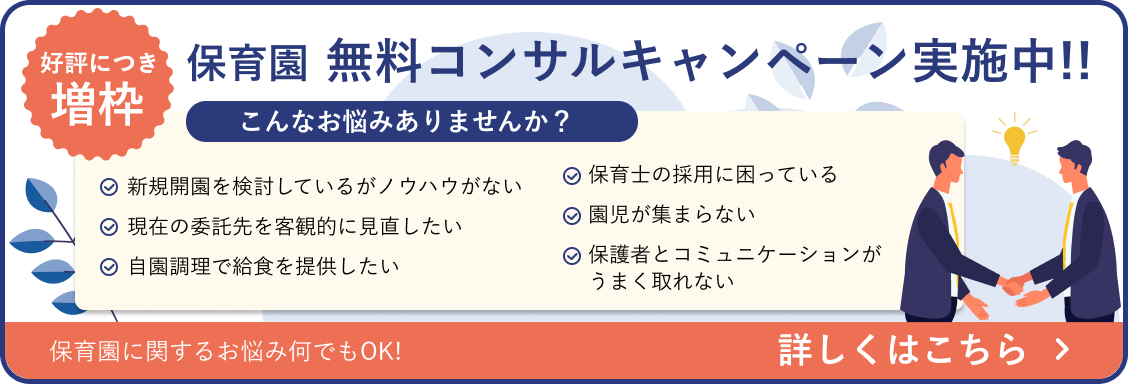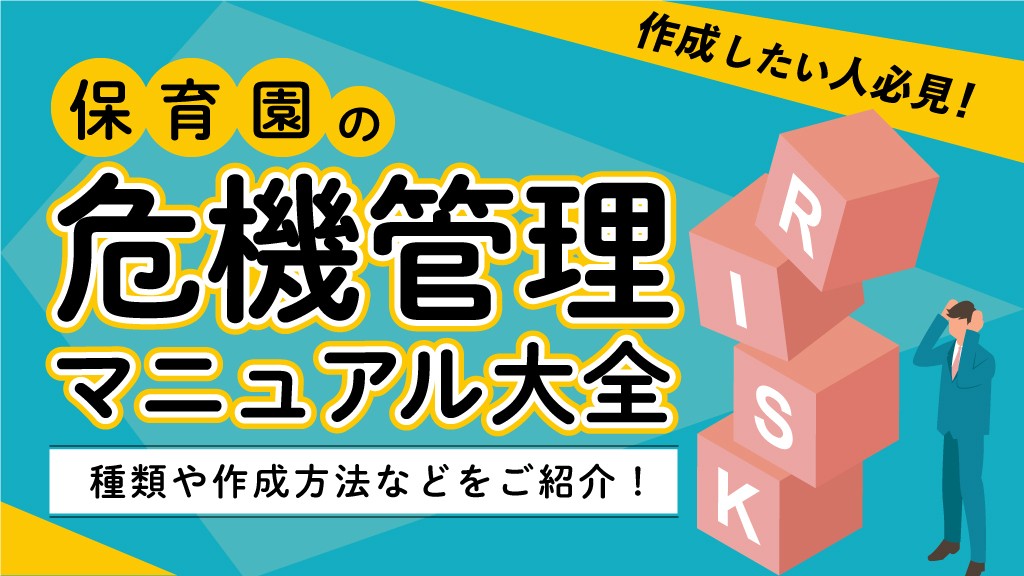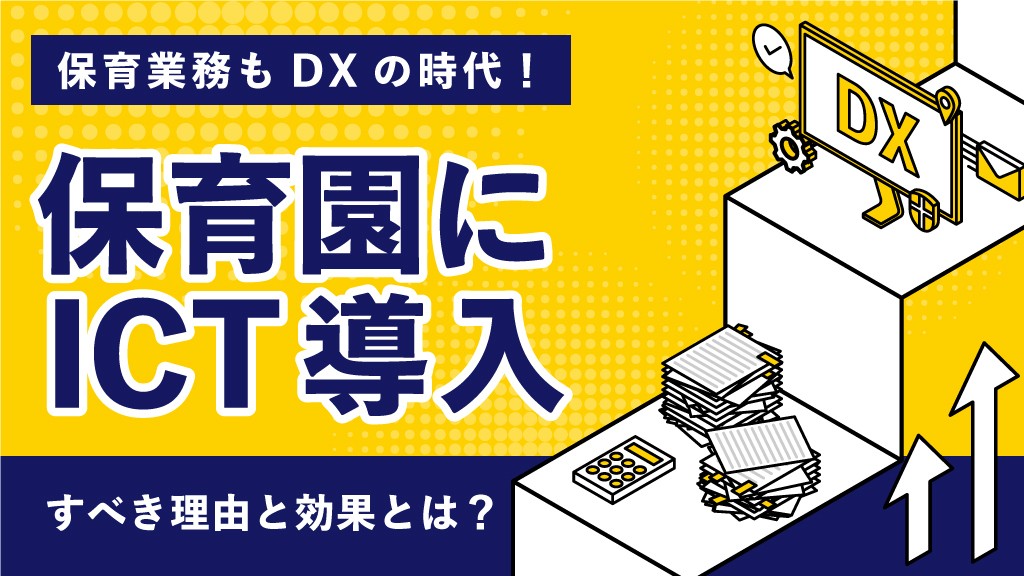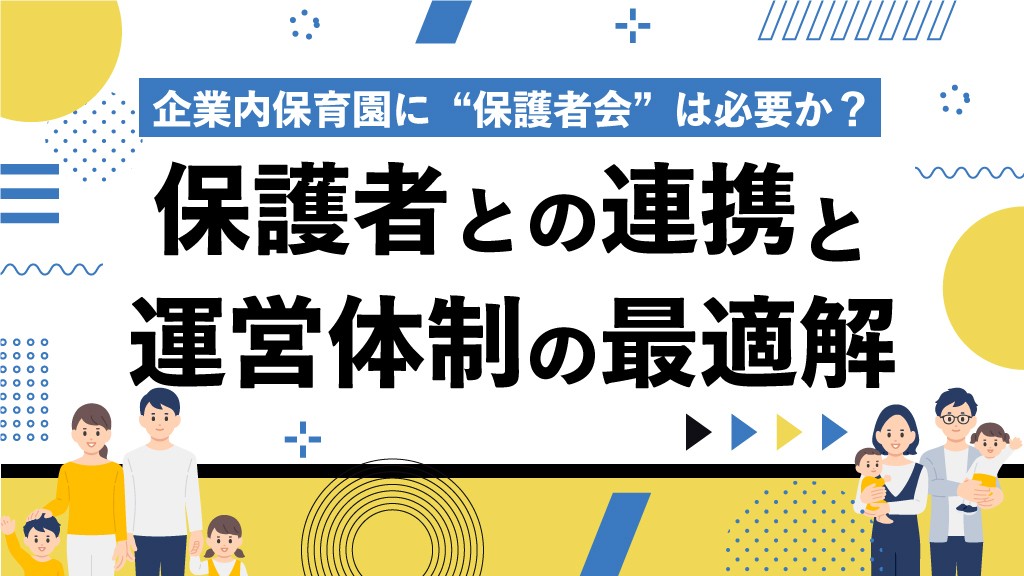保育園運営の委託費用はどれくらい?相場・内訳・コスト最適化のポイントを解説
本記事は、これから委託を検討している方、すでに委託しており比較を検討している方に向けて、主にその費用の相場や内訳、コストを最適化しスムーズな運営を実現するポイントを解説します。
さらに、導入事例や注意点も紹介し、お役に立てる内容にできればと考えています。
目 次
- 1. 保育園の「委託運営」とは?基本からおさらい
- 1-1. そもそも委託運営とは?
- 1-2. 委託運営が選ばれる背景
- 1-3. どんな企業・病院に選ばれているのか
- 2. 保育園の委託費用、相場はどれくらい?
- 2-1. 委託費用の「平均的な相場感」
- 2-2. 委託費用はどう決まる?見積もりの内訳
- 2-3. 法人によって費用が大きく異なる理由
- 3. コストに影響を与える3つの要素
- 3-1. (1)園の規模(定員)
- 3-2. (2)保育時間帯とシフト構成
- 3-3. (3)人材確保の難易度
- 4. コストを抑えながら“質”も確保するポイント
- 4-1. 助成金・補助金の活用を前提にする
- 4-2. 委託業者の選定基準を明確にする
- 4-3. 初期費用・運営費のバランスで最適化を図る
- 5. 委託を検討する前に押さえたい注意点と落とし穴
- 5-1. 最初に「委託で何を解決したいか」を明確に
- 5-2. 見積もりの読み方|安い=コスパではない
- 5-3. 契約時に確認すべき項目
- 6. まとめ|費用感を理解した上で最適な委託方法を選ぼう
- 6-1. 費用相場を知ることが第一歩
- 6-2. 制度を踏まえ、無理のない運営を
- 7. 保育園運営の専門家に無料で相談

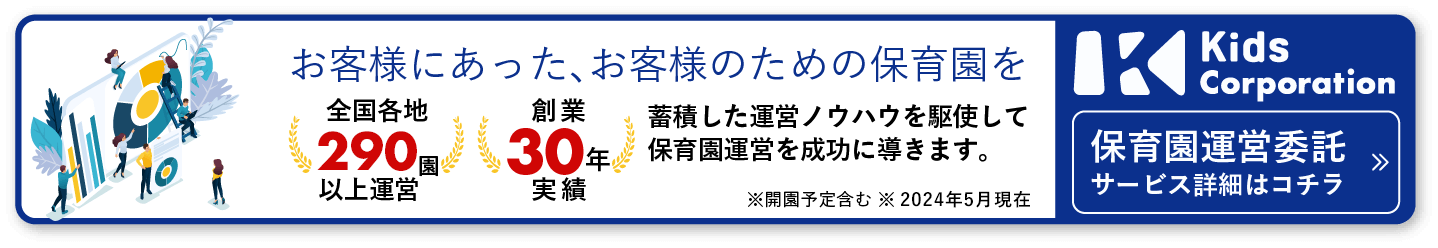
保育園の「委託運営」とは?基本からおさらい
そもそも委託運営とは?
委託運営は、設置者である法人様が建物などのハード面のみを用意し、保育士の雇用、運営管理、カリキュラム作成、保護者対応など、保育園運営に関する業務全般を、専門の運営業者に一括して任せる形態です。
直営の場合、上記をすべて担当する職員が担う事となりますが、委託により運営負担から解放され、本業にリソースをあてることが出来ます。
また、専門である委託業者のノウハウにより、質の高い保育を実現することができます。
委託運営が選ばれる背景
委託運営が選ばれる主な背景としては、全国的な保育士不足と採用難 、保育園運営に必要な専門ノウハウの不足 、そしてコンプライアンス強化と事故防止・リスク管理の必要性(企業主導型保育事業の厳格な監査など )などが挙げられます。
これらの課題を外部の専門家に任せることで、企業は本業に集中し、リスクも軽減できます 。
どんな企業・病院に選ばれているのか
委託運営は、多様な企業や病院で導入されています。
医療法人は24時間保育などのニーズが高く、離職防止や人材確保に貢献 しています。
大手企業は従業員エンゲージメント向上やダイバーシティ推進の一環として導入し、質の高い保育を重視 しています。
中小企業は限られたリソースで福利厚生を充実させるため、企業主導型保育事業の活用と運営負担軽減を目的としています 。
保育園の委託費用、相場はどれくらい?
委託費用の「平均的な相場感」
保育園運営の委託費用は、園児数が増えるほど人件費が増加し、それに伴い費用も高くなります。
例えば、園児10人規模で月額約120万~150万円 、20人規模で月額約250万~300万円 が目安です。
ただし、地域差(都市部の人件費高騰 )、開園時間(夜間・早朝保育は手当発生 )、給食提供の有無も費用に大きく影響します 。
委託費用はどう決まる?見積もりの内訳
委託費用は主に人件費、施設運営費、管理・監修費で構成され、その約8割を人件費が占めます 。
●人件費(保育士・事務職)
人件費は保育士、調理員などの給与、手当、社会保険料を含み 、公定価格の約80%が目安です 。
保育士一人当たりの年間人件費は約490万円から460万円とされます 。
配置基準や賃金体系が費用に直結するため、適正性の見極めが重要です 。
●施設運営費(光熱・消耗品・給食)
光熱費、通信費、消耗品費、遊具費、給食費などが含まれます 。
給食費は食材費、調理業務、衛生管理(HACCP対応 )などを含み、自園調理か外部搬入かで費用が変動します 。
●管理・監修費(マネジメント・法対応)
委託会社が運営全体をマネジメントし、品質維持、法規制対応にかかる費用です 。
専門性や実績、トラブル対応能力の対価であり、見積もりでは内訳の透明性確認が重要です 。
●公定価格と委託費の関係性
認可保育園や企業主導型保育事業では、国が定める「公定価格」が運営費の基準となります 。
公定価格は基本分単価と加算項目で構成され 、委託費の適正性を判断するベンチマークとなります。
法人によって費用が大きく異なる理由
委託費用が法人によって異なるのは、保育士の配置基準、開園時間、そして補助金や助成金の活用状況が主な要因です。
●保育士配置基準と人件費への直接的な影響
保育士の配置基準は子どもの年齢によって異なります。
特に0歳児(園児3人に対し保育士1人)や1・2歳児(園児6人に対し保育士1人)といった乳児が多いほど、より多くの保育士が必要となり人件費が高くなります 。
園児の年齢構成が費用を大きく左右します。
●開園時間、夜間保育、早朝保育の有無によるコスト変動のメカニズム
延長保育や夜間・早朝保育は、通常の勤務時間外手当や深夜手当が発生するため、人件費が大幅に増加します 。
利用者が少ない時間帯の「待機コスト」も発生するため、利用見込みの正確な予測と費用対効果の評価が必要です。
●補助金・助成金の活用状況と企業主導型保育事業の有無
「企業主導型保育事業」は、施設の整備費と運営費に助成金が支給され 、企業の費用負担を大幅に軽減します 。
自治体独自の補助金も活用可能ですが 、助成金には5年で打ち切られるリスクや、要件遵守の厳しさ、集客リスクなどの注意点があります 。
コストに影響を与える3つの要素
(1)園の規模(定員)
園の定員数が増えるほど、必要な保育士の総人件費は高くなります。
しかし、園児一人当たりの管理費や施設維持費は相対的に低減し、コスト効率が向上する可能性があります 。
特に乳児の割合が高い園は、より多くの保育士が必要となり人件費が高騰します 。
(2)保育時間帯とシフト構成
延長保育や夜間・早朝保育では、時間外手当や深夜手当が発生するため、人件費が大幅に増加します 。
利用者が少ない時間帯の「待機コスト」も考慮が必要があります。
委託会社は効率的なシフトで人件費の最適化を図りますが、保育士の労働条件や法令遵守も重要となります。
(3)人材確保の難易度
保育士の採用難易度は地域によって異なり、都市部は競争が激しく人件費が高くなります。
地方は、母数が少ない中から人材確保をしていく必要があります 。
採用に強い委託会社は、独自のネットワークや研修制度で安定的に質の高い保育士を確保し、企業側の採用コストを削減できます。
一方、採用力が低い業者を選んでしまうと、保育士不足による運営不安定化や追加コストが発生するリスクがあります 。
コストを抑えながら"質"も確保するポイント
助成金・補助金の活用を前提にする
「企業主導型保育事業」は、施設の整備費と運営費に助成金が支給され 、企業の費用負担を大幅に軽減できます 。
2025年度には延長保育の支給要件緩和や補助単価引き上げも予定されています。
*2022年度以降、新規開設は行っておりません。
自治体の補助制度として、認可外保育所への補助が各地で整備されています。
また、地域型保育事業の新規開設、認可外保育園からの移行は自治体により現在も進められています。
地域型保育事業とは、小規模保育事業や家庭的保育事業、事業所内保育事業などのような1人~19人程度の小規模の保育事業に対して、市区町村による認可事業として多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みです。
自治体からの助成金を受けながらの保育園運営を目指せるのが大きなメリットですが、申請手続きが煩雑であることに加え、開園後は認可保育園と同等の基準や質を求められます。
委託会社によっては、認可取得からのサポートも行います。
委託業者の選定基準を明確にする
「安さだけ」で業者を選ぶと、品質低下や隠れたコスト(集客支援不足、トラブル対応不足など)が発生し、結果的に総コストが高くなるリスクがあります 。
【品質チェックのポイント】
委託業者を選定する際は、以下の点を総合的に評価することが重要です。
●受託実績: 自社の業態や地域に合っているか。
●保育の質: 保育方針、カリキュラム、安全管理体制はどうか。
●柔軟な対応力: 就業時間や個別の要望に柔軟に対応できるか。
●リスクマネジメント体制: 事故対応やコンプライアンスへの意識は高いか。
複数の会社から見積もりを取得し、その内訳やサービス範囲だけでなく、上記のような価格以外の要素も比較検討しましょう。
初期費用・運営費のバランスで最適化を図る
保育園設置の初期費用は建設費(1坪あたり約80~120万円 )と備品費(200万~300万円 )で構成されます。
施設の建設・内装工事と運営委託を別々に依頼する「分離型」は自由度が高い一方、委託会社が一貫して請け負う「一括型」は手間を省くことができます 。
費用対効果は短期的なコストだけでなく、従業員の定着や採用力強化といった「人的資本への投資」として長期的な視点で評価すべきです 。
委託を検討する前に押さえたい注意点と落とし穴
最初に「委託で何を解決したいか」を明確に
委託運営を導入する際は、その目的(福利厚生、人材確保、企業イメージ向上など)を明確にすることが重要です。
目的が曖昧だと、費用対効果が見えにくくなり、導入後に「利用者が集まらない」「助成金が下りない」「事故対応が不十分」といった問題が発生するリスクがあります 。
見積もりの読み方|安い=コスパではない
見積もりは「安さ」だけでなく、内訳(人件費、施設運営費、管理・監修費 )、請求方法、サービス範囲、隠れたコストの有無を詳細に比較分析することが不可欠です 。
委託業者との関係は長期にわたるため、保育の質、サポート体制、実績、評判といった価格以外の要素も重視して評価すべきです 。
契約時に確認すべき項目
委託契約では、運営トラブル時の「責任分界点」を明確にすることが極めて重要です 。
最終的な法的責任は設置者に帰属することを理解しつつ 、委託会社の過失範囲や対応プロトコルを確認します 。
保育士の採用責任、配置人数の確約、採用が難航した場合の対応策も契約に盛り込むべき必須項目です 。
また、契約解除条件、反社会的勢力排除条項 、運営状況や財務状況の情報共有体制も明確に定めておくと良いです。
まとめ|費用感を理解した上で最適な委託方法を選ぼう
費用相場を知ることが第一歩
保育園運営の委託費用は、園児数、開園時間、サービス内容、地域、助成金活用状況といった多様な要素で変動します。
提示された金額だけでなく、サービスの質、専門性、リスク管理能力、長期的なパートナーシップの可能性を多角的に評価することが、最適な委託先を選ぶ上で不可欠です。
制度を踏まえ、無理のない運営を
自社の状況に合ったモデルを見つけることが成功への鍵となります。
地域型保育事業や企業主導型保育事業などの助成金は費用負担を軽減する強力なツールですが、期限や要件があるため、長期的な財源確保とリスク管理が重要です 。
また、契約時の責任の分界点の明確化は、将来的なトラブルを防ぎ、安心して運営を継続するために不可欠です。
保育園運営の専門家に無料で相談
保育園運営に関わる会社・サービスは多く存在しますが、これから保育園の新設、委託切り替えを検討されている方はぜひキッズコーポレーションへご相談ください!
当社は全国356園以上の保育園を運営しており、病院様や企業様の保育園開設・運営を多数お手伝いさせていただいております。
そのノウハウを活かして「どの制度で開設すべきなのか」「失敗しない保育園開設の流れ」等、開設にあたってのアドバイスを無料で行なっております。
「気になるけどいきなり相談はちょっと…」という方は無料でダウンロードいただける資料をご確認ください。